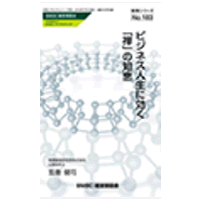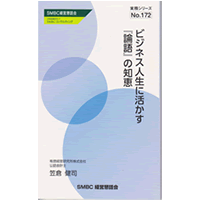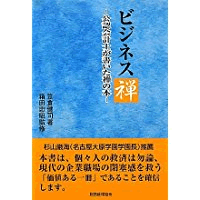無門関第35則「せい子が二人に分身した」
さて、柴山老師が『無門関講話』の中で、この公案に関して、普融知蔵(ふゆう-ちぞう)和尚の詩を紹介されています。
普融知蔵(ふゆう-ちぞう)は、法演禅師(ほうえん-ぜんじ)のもとで、この「倩女離魂(せいじょ-りこん)」の公案によって大いに苦労して修行しました。
そして、ついに大悟して、次の詩を残したと伝わっています。
<普融知蔵(ふゆう-ちぞう)の偈(げ)>
二女が合して、一婦人となる。
働きは終り、もはや何の出入りもない。
行くも帰るも、跡(あと)かたもない。
旅人よ、昔どの道を来たかと、問うてくれるな。
この詩の意味は、
「二人の倩女(セイ子)が合して、一人の嫁女となった。
この絶対主体の一者となってしまった端的(たんてき)は、
筆舌(ひつぜつ)の及ぶところではない。
ただこのとおり――何の分別も入りようがない。
さて、この絶対主体の一者になりきってみれば、
元来、行くも帰るも、自も他も、跡(あと)かたさえない。
人々よ、かつてどの道を来たか?と聞いてくれるな。
そんな昔の消息など、知るはずはないではないか。」
『無門関講話』(柴山全慶著・創元社)
「この絶対主体の一者となってしまった端的(たんてき)」とは、悟り体験のことを指しています。そこは、「何の分別も入らない」という透明な澄み切った心境で、言葉では表現できないといっています。
「悟り」の心境においては、自と他の対立もないのですが、いったん「悟り」体験をすると、世界の見方や感じ方が大きく変わります。
なぜ変わったのか?と問われても、自分でも、うまく説明できません。そのことを「かつてどの道を来たか?と聞いてくれるな。」とうたっています。
このような悟りの世界に導いてくれる糸口になるのが、この公案であるということでしょう。
「セイ子が二人に分身した」というのは、じつは、精神と物資、心と肉体が分裂し、分離し、時に対立して、心がヘトヘトになっている人を象徴しているのだと思います。
もちろん、これは他人事ではありません。私たち凡夫が、悩みや悲しみや怒りに心を囚われているとき、心が肉体を苦しめ、胃が痛んだり、頭が痛んだりします。
ときに、うつ病になり、胃潰瘍になり、高血圧になったりしますが、その原因のかなりの部分は、ストレスにとらわれた心だったりします。そのとき、私たちの心と肉体は、分離しているわけです。それを統一して、心身を健康にするのが、坐禅であり、瞑想であり、祈りなのだと思います。
<9月のイス禅セミナー:ご案内>
イス禅と禅仏教の古典(『無門関』など)に学ぶセミナーを
9月17日(水)に、秋葉原駅近くの区民会館で開催します。
前半は、誰でもできるイス禅瞑想の実修です。
休憩後の後半は、禅の古典からの講話となります。
禅に関心のある方は、どなたでも参加できます。
日時:2014年9月17日(水)19時~21時(開場18時30分)
場所:JR秋葉原駅そばの「和泉橋区民会館」
(千代田区立の公民館)