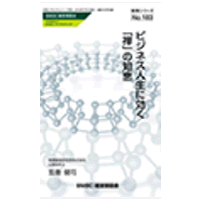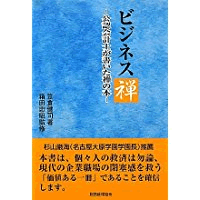大動乱の時代に皇帝を指導した禅師
六祖慧能(ろくそ-えのう)は、優れた弟子を何人も育てましたが、その中には、「国師(こくし)」(皇帝の師)となった弟子がいました。それが慧忠(えちゅう)です。
慧忠は、八世紀の中国・唐(とう)時代に、粛宗(しゅくそう)及びその子の代宗の二代の皇帝から参禅の師とあおがれた人です。禅宗が盛んになった唐代から宋代にかけて、「国師」となった禅僧は何人もいますが、後世の禅宗では「国師」といえば、慧忠を指すほど大きな存在です。(「黄門(こうもん)」といえば、水戸光圀を指すのと同じでしょう。もともと「黄門」とは、日本で中納言になった人に対する唐様の呼び名ですが、水戸光圀の存在が大きいために、光圀の別名として固有名詞のように使われています。)
さて、日本から遣唐使が送られたのでも分かるように、唐(六一八年~九〇七年)は、当時、世界最大の大帝国でした。しかし、どのような大帝国にも栄枯盛衰がつきものです。唐の国力は、楊貴妃(ようきひ)とのラブロマンスで有名な玄宗(げんそう)皇帝(在位七一二年~七五六年)の時代が最盛期でした。玄宗の治世の終盤になると政治が乱れ、ついに安禄山(あんろくさん)によって国中を揺るがす大反乱が起きます。(安史の乱・七五五年~七六三年)
安禄山の攻撃によって、玄宗皇帝は長安の都から蜀(四川省)に逃げ出しました。反乱軍によって皇帝が都から逃げざるをえなかったほどですから、唐王朝はまさに滅亡の危機にありました。
その国難のときに、父親の玄宗から皇位を譲られて皇帝に即位したのが、慧忠に師事した粛宗(在位七五六年~七六二年)です。粛宗は討伐軍を指揮して反乱軍と戦い、ついに都の長安を奪還します。しかし、激しい内乱は粛宗の寿命を縮めたようで、わずかに在位六年で亡くなりました。その後を継いで安史の乱を終結させたのが、息子の代宗(在位七六二年~七七九年)でした。
粛宗も代宗も大動乱の時代に生き、北方のウイグル帝国の力を借りて反乱軍を鎮圧し、平和を取り戻しました。しかし、その過程でウイグルなど近隣異民族の力が伸びて、安史の乱後は、近隣諸国を抑えるのに大変苦労することになります。また、動乱の中で各地に軍閥ができたことも、唐王朝の力を弱めることになりました。
そのため、玄宗の治世におけるような平和で安定した時代を再現することはできず、粛宗も代宗も、皇帝として大変な苦労をしました。日本でも元寇(げんこう)の危機の時に執権の北条時宗が熱心に禅に参じた例がありますが、大きな国難に直面した皇帝だからこそ、慧忠を心の師と仰いで参禅したのでしょう。
■粛宗の自己点検の問い
さて、慧忠と粛宗皇帝(しゅくそうこうてい)との禅問答が伝わっています。ある日、粛宗(しゅくそう)が、
いかなるか、これ、十身(じゅっしん)調御(ちょうご)?
(現代語訳)
仏様の十変化とは、いかなるものでしょうか?
と慧忠に問いました。
華厳経(けごんきょう)の中に、「仏様は悩める人々を救うために、十通りも姿を変える」と書かれています。仏様の多面的で優れた働きを称える表現です。禅を真剣に学んでいた粛宗は、それを踏まえて、「私も皇帝として、仏の十変化なみに、四方八方に目を配った十分な働きができていると思いますが、いかがでしょうか?」と慧忠に質問しました。
粛宗(しゅくそう)は皇太子時代から慧忠の下で何年も禅の修行をしてきた人ですから、初心者が問う基本的な質問をしたわけではありません。自分のこれまでの禅の学びや人生経験を踏まえて、これまで学んできた禅の教えを現実に活かしているかどうか?を慧忠国師に点検して欲しいという趣旨です。
この問いに対して慧忠は、
毘盧(びる)頂上を踏んで行け!
(現代語訳)
毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)の頭を踏んでいきなさい。
と答えました。
毘盧遮那仏は、『華厳経』に説かれている「宇宙の真理を照らし、人々を悟りに導く仏様」のことです。私たちになじみ深いものとしては、奈良の東大寺の大仏が毘盧遮那仏です。東大寺の大仏は、七五二年に完成していますので、慧忠国師や粛宗と同時代の仏象です。当時、毘盧遮那仏は、最高の仏様として、広く信仰を集めていたのでした。
その「毘盧遮那仏の頭を踏んでいきなさい。頭を踏み越えて、仏様の上に行きなさい!」とは、熱心な仏教徒からみれば、恐ろしいほどの答えです。禅的な意表を突く表現ですが、慧忠の意図は、「仏様の十変化のような働きをしておりますか?などという抹香(まっこう)臭い、仏教かぶれの考えではダメじゃ。」ということでした。
しかし、その意表を突く表現に、禅を長年学んできた粛宗にも、慧忠の真意が分かりませんでした。そのため、粛宗は、「私には、老師のおっしゃることが一向に分かりません。さらにご教示ください。」と素直に答えました。
■悟りを忘れるのが、禅
「仏の頭を踏み越えていけ!」という慧忠の答えは、「禅の教えをありがたそうに考えていると、禅に捉われますぞ!ありがたそうなものを乗り越えていくのが、本当の禅だ。」という意味です。
慧忠の答えは、禅の専門書では、「相手が皇帝だからといって、親切すぎるくらい柔らかい答えだ」とされています。もし、雲水が相手ならば、もの柔らかに言葉で答えずに、いきなり「喝アアアーッ」と怒鳴られていたか、あるいは、突き飛ばされていただろうといわれます。
これは、皇帝だからといって、慧忠が遠慮したわけではなく、「人を見て法を説く」という言葉を実践した結果です。周りの人から、いつも奉られている皇帝をいきなり怒鳴っても、相手の心に届かないと見て、慧忠は柔らかい言葉で教え諭そうとしたのでした。
しかし、粛宗が理解できないのを見て慧忠は、さらに言葉をつづけました。
自己(じこ)清浄(しょうじょう)法身(ほっしん)を認むるなかれ!
(現代語訳)
「自己が清浄法身である」などと、悟り臭いことではいけませんぞ。
自分の悟りにしがみつかずに、その悟りを捨てなさい。
清浄法身とは、善も悪もない絶対的に清らかな心の本体という意味です。禅では、「誰もが生まれながらに仏様と同じ絶対的に清らかな仏心を持っている」と教えます。
人間は、本来、仏様と同じ清らかな仏心を持っているのに、むさぼり・怒り・ 愚かさなどの煩悩(ぼんのう)によって心の本体を見失っていると、禅では考えます。そこで「心をみがいて、まず清らかな心の本体に気づく」ということが、禅修行の最初の目標になります。
粛宗は若い皇太子の時代から熱心に禅を学んで来た方ですから、「誰もが仏様と同じ清らかな仏心を持っており、自分も確かにそれを持っている」という初歩の悟りを得ていました。それに対して、慧忠は、「あなたの悟りを捨てなさい」と指導したのでした。
基本の悟りを得るだけでも、普通は大きな自信になり、ストレスに強い心になれるものです。しかし、一つの段階に達すると、しばしば、そこに捉われて、次の段階に進めなくなるのが、人間の性(さが)でもあります。
粛宗(しゅくそう)が基本の悟りに捉われていると見た慧忠は、さらなる進歩を促すために、「仏様の頭を踏み越えろ!」という表現で、「今の自分に満足しないで、さらにそれを乗り越えなさい。」と示したのでした。
■非常時に必要な決断力と平常心
粛宗の六年間の治世は、平穏無事な時代ではありません。粛宗が即位したときは、皇太子として父親の玄宗とともに都の長安から蜀(四川省)へ敗走する途中でした。
敗走途上の馬嵬(ばかい)で、皇帝の身辺を守る近衛兵が反乱を起こし、玄宗が信頼していた宰相の楊国忠(ようこくちゅう)が安史の乱を招いた責任者として殺されました。さらに、近衛兵の要求で、玄宗が最も愛した楊貴妃(ようきひ)も死刑にされます。そのような危機的状況で、玄宗から位を譲られて即位したわけですから、粛宗が凡庸な人でおろおろしていれば、その時点で唐王朝は滅んだかもしれません。
さらに、弱体化した唐軍だけでは反乱軍に勝てないと判断し、異民族であるウイグル帝国と提携するという困難な決断をしました。反乱を起こした安録山(あんろくさん)がソグド人という異民族出身でしたから、異民族に対する警戒心が強かったときです。毒を持って毒を制する策ですが、ウイグルに大きな借りを作ることになりますから、朝廷内に反対意見も強かったでしょう。粛宗は反対を抑える必要がありました。これもトップが平常心を欠いたら、とてもできないことです。
名将の郭子儀(かくしぎ)を見出して、討伐軍の指揮を取らせたことも大きな決断だったと思われます。郭子儀(かくしぎ)は、安史の乱を平定するのに最も功績のあった武将で、後世では、中国史上、屈指の名将と評価されています。しかし、五十代まで地方の軍司令官を務めていた大器晩成型の人物で、討伐軍の将に起用された当初は、かなりの抜擢人事でした。非常時とはいえ、粛宗に決断力がなければできないことだったでしょう。
唐王朝存亡の危機を乗り越えるためには、粛宗はいくつもの困難な決断をしなければなりませんでした。平時では考えられないほどの精神力を要請される状況です。そのようなときに皇太子時代から学んできた禅の教えが心の支えとなったでしょう。
企業に例えれば、時代環境が変わって、それまでのビジネスモデルではやっていけなくなって倒産の危機に陥り、突然、高齢の前社長から若手に社長交代したようなものです。新社長はいやでも企業体質の変革に取り組まなければなりません。そのような非常時こそ、トップの強いリーダーシップが求められます。
そのような危機的状況を次々と乗り越えて、都の長安に戻ってから、粛宗と慧忠の禅問答があったのでした。まだ反乱軍の討伐が完了していないとはいえ、都を取り返したわけですから、粛宗は相当の自信をもっていたでしょう。だからこそ、自分を「仏様の十変化」にたとえることができたのだと思います。
粛宗は、国難を乗り越えるだけの強い心を養えているかどうかを慧忠に点検してもらいたかったのでしょう。滅びかけた唐王朝を立て直しつつある粛宗の実績を考えれば、大いに褒めてもよい場面です。
しかし、慧忠は、あえて粛宗にダメ出しをしています。自己満足に陥ることを諫めたのでしょう。慧忠は、粛宗の置かれた困難な状況を理解した上で、非常時のリーダーの心得を諭したと思われます。
慧忠は粛宗のさらなる活躍を祈りつつ、「非常時には大きな決断が必要になる。自分の思い込みに囚われてはいけない。仏様の頭を踏み越えて行くような思い切った変化や決断を恐れないように!」というアドバイスを与えました。思い切った決断は、すでに粛宗が十分に経験してきたことですが、このような注意は、慢心しかけたときほど価値があります。
「現状の成果(悟り)にとらわれずに、それを忘れることが大事だ」という慧忠の教えは、その核心部分が禅の公案として、今日でも学ばれています。困難に直面しても、恐れずに正々堂々とこれに取り組み、知恵をしぼって新しい道を切り拓いていく勇猛心をこの禅話から学びたいものです。